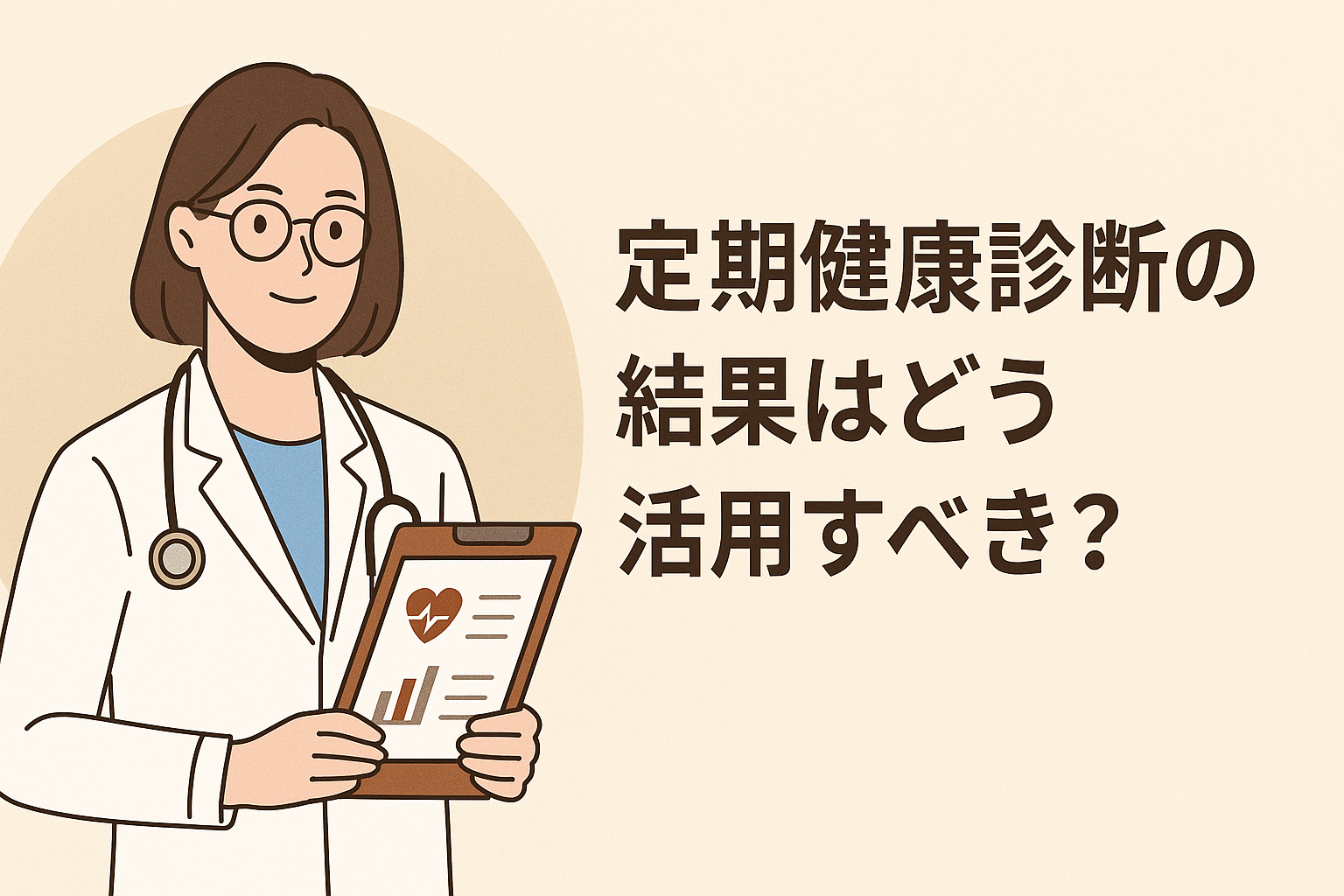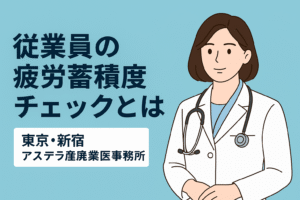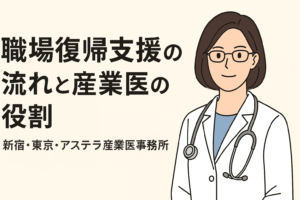企業が毎年実施する「定期健康診断」。実施後の結果はどのように活用されていますか?「やって終わり」では、労働安全衛生法上の義務を果たしたとは言えません。企業にとって、健康診断の結果を適切に活かすことは、従業員の健康保持はもちろん、業務効率や企業価値向上にもつながります。
本記事では、健康診断結果の正しい活用方法や、産業医の役割について、初心者にもわかりやすく解説します。新宿・東京で活動するアステラ産業医事務所の取り組みもご紹介します。
健康診断結果を「見て終わり」にしない
多くの企業では、健康診断を毎年実施しても、結果を配布して終わりというケースが少なくありません。しかし、労働安全衛生法第66条に基づき、事業者は以下の義務を負っています。
- 健康診断の実施
- 医師による意見聴取
- 就業上の措置(必要に応じて)
- 記録の保存(5年間)
つまり、健康診断結果は、企業が従業員の健康リスクを把握し、必要な対応を講じるための「スタートライン」に過ぎないのです。
健康診断結果の活用方法
① 産業医による意見聴取
健康診断後には、結果の内容を産業医が確認し、「就業上の措置が必要かどうか」の医学的判断を行います。企業の人事・総務担当者は、この意見を受けて適切な対応を行う必要があります。
② 健康リスクの集団分析
個人の診断結果だけでなく、部門別・年代別などで集団的な健康リスク分析を行うことで、企業全体の課題を可視化できます。例えば、30代男性に高血圧傾向が多い、40代女性に肥満傾向が多いなど、対策の優先順位づけに活かせます。
③ ハイリスク者へのフォローアップ
高血圧・高血糖・肥満・肝機能異常などのハイリスク者には、産業医面談を実施し、生活改善指導や医療機関受診勧奨を行います。放置すれば、脳卒中や心筋梗塞といった重篤な疾患リスクが高まるため、早期介入が鍵です。
④ 就業上の措置と職場環境の改善
診断結果や面談を踏まえて、必要に応じて勤務時間短縮・作業内容の変更・配置転換などの就業措置を講じます。また、社内全体として、食事指導や禁煙支援、運動促進などの健康施策を計画することも有効です。
産業医の役割と企業の体制整備
産業医は、健康診断結果に基づいて、医学的立場から就業可否の判断や健康指導を行います。企業は、以下の体制を整えることが重要です。
- 健康診断後の結果一覧の提出・共有
- 産業医との面談設定(特に所見あり対象者)
- 医師の意見を踏まえた就業措置の実行
- フォロー面談の記録と継続的管理
健康診断後の対応をおざなりにすると、労基署からの是正勧告対象となる場合もあります。
定期健康診断とメンタルヘルス対策の連携
健康診断では身体の状態が主な評価対象ですが、昨今はメンタルヘルス不調の見逃しが問題になっています。健康診断の問診結果や休職歴などから、メンタル面の不安がある従業員を早期に把握し、産業医による面談につなげることが重要です。
また、年1回のストレスチェック制度と連動させることで、より包括的な健康管理体制が構築できます。
参考:復職支援の進め方と注意点
東京・新宿で産業医支援をお探しの企業様へ
アステラ産業医事務所(東京都新宿区)では、定期健康診断後の結果管理・産業医意見聴取・面談対応・健康リスク分析・職場改善提案まで、総合的なサポートを提供しています。
実務対応に追われるご担当者様に代わり、企業の健診活用を仕組みとして支援します。詳細はアステラ産業医事務所のホームページをご覧ください。
まとめ:健診結果を“生きた情報”として活かす
健康診断は、ただの形式的な業務ではなく、従業員の命を守る大切な機会です。健診結果を正しく活用し、産業医との連携を深めることで、従業員が安心して働ける環境が整います。
新宿・東京エリアで健康診断後の対応や産業医支援にお困りの方は、アステラ産業医事務所へぜひご相談ください。