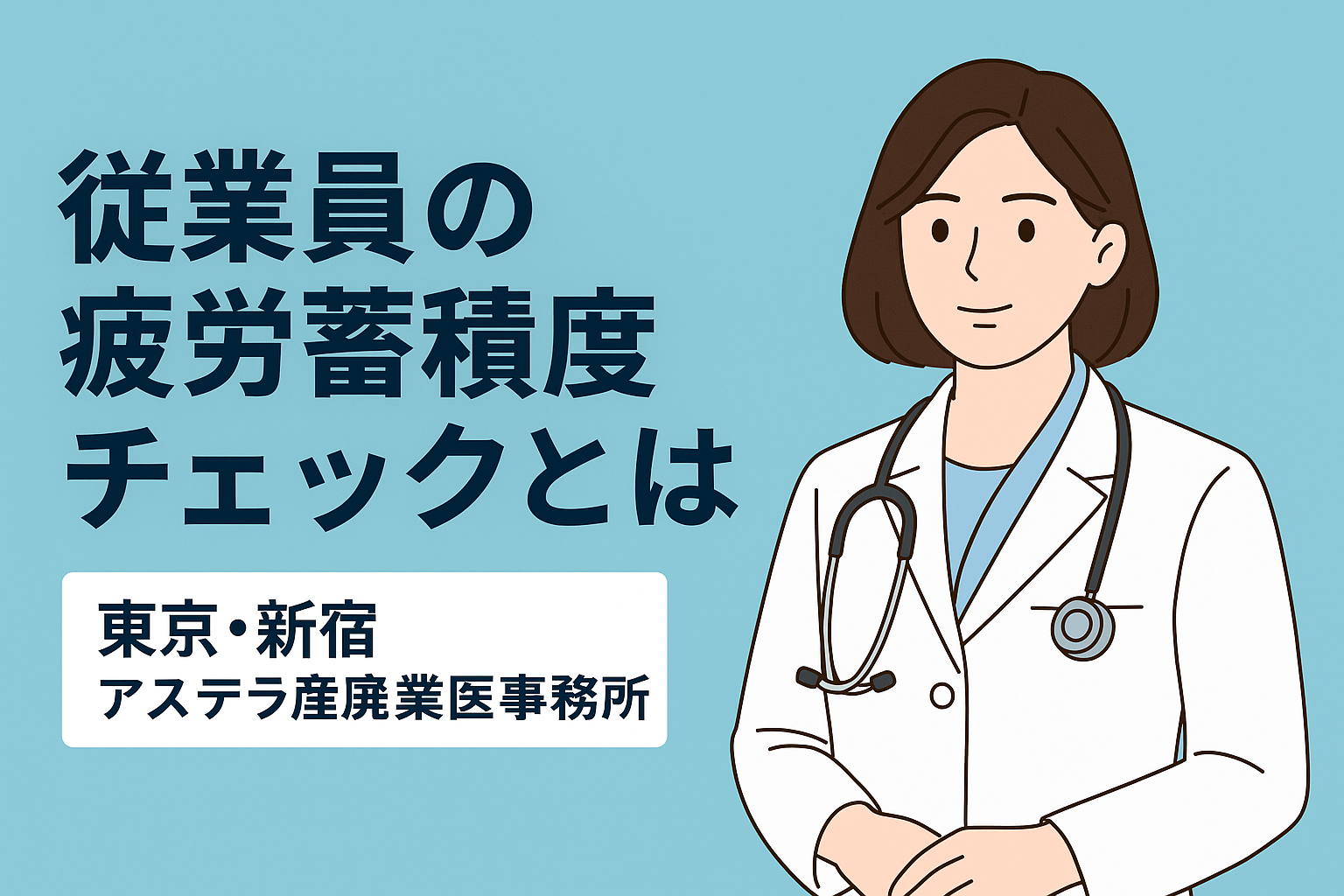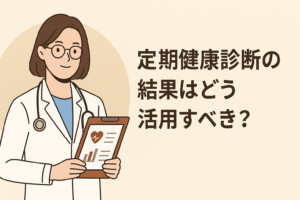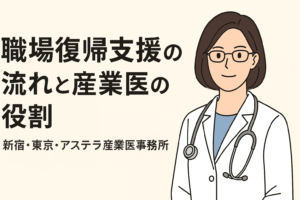長時間労働やストレスが重なる現代のビジネス環境では、従業員の「疲労蓄積」が深刻な健康リスクとなっています。そこで注目されているのが「疲労蓄積度チェック」です。特に、労働安全衛生法や厚生労働省のガイドラインを遵守する上でも、企業の健康管理体制に欠かせない仕組みとなっています。
本記事では、疲労蓄積度チェックの概要と導入方法、産業医の役割を、初心者の人事・総務担当者や経営者向けにわかりやすく解説します。新宿・東京エリアで活動するアステラ産業医事務所の事例も交えてご紹介します。
疲労蓄積度チェックとは?
「疲労蓄積度チェック」とは、従業員が過重労働やストレスにより健康障害を起こす前に、疲労の蓄積状況を可視化し、必要な対策を講じるための評価ツールです。厚生労働省が示す「過重労働による健康障害防止のための総合対策」でも、このチェックの活用が推奨されています。
特に以下のような目的で導入されます。
- 健康障害リスクの早期発見
- 長時間労働者に対する医師面接指導の必要性判定
- 産業医面談や健康管理施策の優先順位付け
- 労働安全衛生法の法令遵守
労働安全衛生法と疲労蓄積度チェック
労働安全衛生法第66条の8では、事業者に対し、一定の長時間労働者に対する医師による面接指導を義務付けています。具体的には、月80時間超の時間外・休日労働が対象です。
しかし、労働時間だけで健康リスクを判定するのは不十分です。そこで、厚生労働省は以下の「疲労蓄積度自己診断チェックリスト」(簡易型)を推奨しています。
このリストを活用することで、労働時間以外の健康要因(睡眠障害・精神症状・生活習慣病リスクなど)も含めた総合的な評価が可能になります。
疲労蓄積度チェックの実施手順
① 対象者の選定
まずは以下のような高リスク者を優先してチェックを実施します。
- 月80時間超の時間外・休日労働者
- 深夜勤務・交代勤務従事者
- 過去に健康障害歴のある者
- 職場ストレスが高い者
② 疲労蓄積度自己診断票の配布・回収
厚労省の標準フォーマットを用いて、定期的に自己診断票を配布し、本人に記入してもらいます。最近ではオンライン化する企業も増えています。
③ 産業医による評価
産業医が記入内容を確認し、医学的リスクを判定します。高リスクと判定された場合は、面接指導や就業上の措置を検討します。
④ フォローアップ
必要に応じて、勤務時間短縮・業務内容変更・ストレスケアプログラム導入など、事業場全体で対策を講じます。
疲労蓄積度チェックを義務化する法律はある?
現在のところ、疲労蓄積度チェック自体は法律上の義務ではありません。ただし、長時間労働者への面接指導義務(安衛法66条の8)や、過重労働防止対策指針の遵守という観点から、事実上必須の実務対応となりつつあります。
厚生労働省の「過重労働による健康障害防止のための総合対策」も参考になります。厚生労働省公式サイト
産業医の役割と連携ポイント
疲労蓄積度チェックにおいては、産業医の専門的な判断が極めて重要です。企業の人事・総務部門は、以下のように産業医と連携する体制を整備しましょう。
- チェック対象者の選定助言
- 診断票評価と高リスク者抽出
- 面接指導の実施
- 就業上の措置案の提示
- 健康教育や職場環境改善の提案
産業医は、労働安全衛生法第13条に定められた企業の健康管理の中心的役割を担っています。
東京・新宿で産業医支援ならアステラ産業医事務所へ
新宿・東京エリアで活動するアステラ産業医事務所では、疲労蓄積度チェックの導入支援、面接指導、健康相談、長時間労働対策を幅広くサポートしています。小規模事業場から大手企業まで、柔軟なプランをご用意しています。
詳しくは アステラ産業医事務所のホームページ をご覧ください。
まとめ:疲労蓄積度チェックは健康障害の未然防止策
疲労蓄積度チェックは、長時間労働による健康障害を防ぎ、従業員の安全と生産性を守る重要な施策です。産業医と密に連携し、法令遵守はもちろん、実効性の高い職場の健康管理体制を