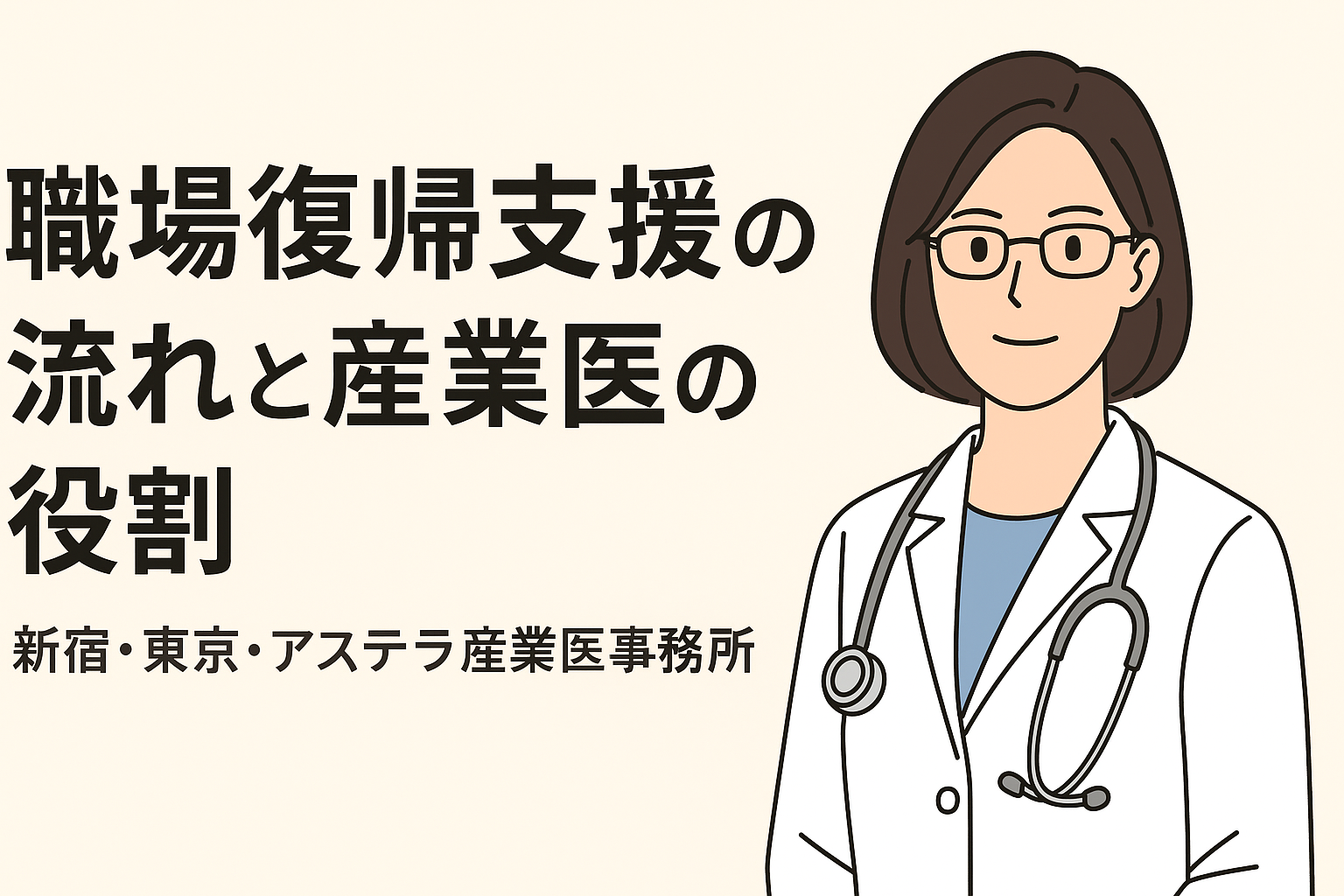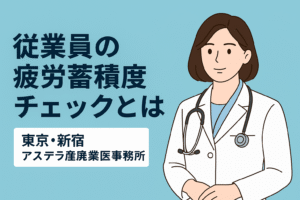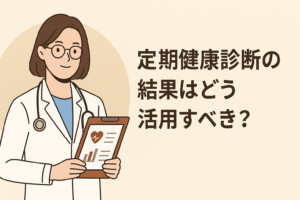現代の職場では、メンタルヘルス不調や長期病気休暇を経験する社員が増加しています。その中で重要となるのが「職場復帰支援」です。職場復帰を円滑に進めるためには、企業・人事担当者・上司だけでなく、産業医の専門的な支援が欠かせません。
この記事では、産業医がどのように職場復帰支援を行い、企業がどのように体制を整えるべきか、最新の労働安全衛生法や厚生労働省のガイドラインを踏まえて詳しく解説します。
職場復帰支援が必要となるケースとは
職場復帰支援は、以下のような状況で必要となります。
- うつ病や適応障害などのメンタルヘルス不調
- 心筋梗塞・脳卒中などの重篤な身体疾患
- がん治療後の復職
- 長期の育児・介護休業明け
特に、うつ病・適応障害などのメンタルヘルス疾患では、再発リスクや業務負荷の調整が必要となるため、復職支援の重要性が高まります。
職場復帰支援の流れ(厚生労働省ガイドライン準拠)
厚生労働省の「心の健康問題により休業した労働者の職場復帰支援の手引き」では、以下のような手順が推奨されています。
① 主治医による復職可能の診断
休業中の社員が主治医から「就業可能」の診断書を取得します。ただし、主治医の診断のみで復職が決定するわけではありません。
② 産業医による復職可否の面談判定
企業内の産業医が面談を行い、医学的・労働衛生的な観点から復職の可否を判断します。確認ポイントは以下の通りです。
- 症状の安定性
- 服薬の影響
- 勤務時間や業務内容の配慮事項
- 再発リスク
産業医は、職場環境や職種の特性も考慮し、総合的に判断します。
③ 職場復帰支援会議の開催
産業医の意見をもとに、人事担当者・上司・労働者本人を交えた「職場復帰支援会議」を開催し、勤務条件(短時間勤務・配置転換・残業制限など)を調整します。
④ 試し出勤・リハビリ出勤の実施
必要に応じて、正式復職前に「試し出勤(リハビリ出勤)」を行い、短時間・軽作業から段階的に勤務を再開します。復職の成功率が高まります。
⑤ 復職後のフォローアップ
復職後も定期的に産業医が面談を行い、体調変化や勤務負荷を確認します。必要に応じた勤務条件の再調整も行います。
産業医の役割とは
産業医は、労働安全衛生法第13条に基づき、企業の健康管理を担います。職場復帰支援における役割は以下の通りです。
- 復職可否判定
- 職場復帰支援会議での医学的助言
- 復職プランの策定・調整
- 復職後のフォローアップ面談
- 再発防止策の提案
- 主治医・職場間の情報調整
また、メンタルヘルス不調の予防として、日常のストレスチェックや職場巡視、教育研修も重要な役割です。
企業が整備すべき職場復帰支援体制
企業側も産業医と連携し、以下のような体制整備が望まれます。
- 職場復帰支援プログラムの策定
- 職場復帰支援会議の設置
- 人事・総務担当者の研修
- 管理職向けのメンタルヘルス研修
- ストレスチェックの活用
厚生労働省のガイドラインに準拠した体制整備は、法令順守だけでなく、従業員の安心感や定着率向上にもつながります。
東京・新宿エリアで産業医をお探しの方へ
東京・新宿を中心に活動するアステラ産業医事務所では、企業の規模や業種に合わせた復職支援プログラムをご提案しています。職場復帰支援に課題を感じている企業様は、ぜひお気軽にご相談ください。
詳細は アステラ産業医事務所のホームページ をご覧ください。
まとめ:職場復帰支援は企業の重要な責任
職場復帰支援は、法律上の義務であると同時に、企業の人材活用・企業価値向上に直結する取り組みです。産業医の専門的支援を受け、柔軟な勤務調整やフォロー体制を整備することで、従業員の再発防止と職場定着が実現します。
アステラ産業医事務所では、職場復帰支援のみならず、日常の健康管理・ストレスチェック・労働衛生全般を総合的にサポートしています。